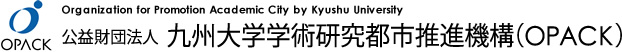
公開日:2025年8月6日
| 開催日 |
2025年9月10日 14:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 開催時間・式次第 | ○セミナー 14時00分から16時30分 (9階913会議室)
○個別面談/名刺交換会 16時30分から18時00分 (3階 会議室) |
| 開催場所 | 日本橋ライフサイエンスビルディング |
| 開催住所 | 東京都中央区日本橋本町2-3-11 |
| お問い合わせ |
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構【担当 藤井】 電話 092-805-3677 FAX 092-805-3678 メールアドレス:seminar2025su@opack.jp |

株式会社Arthron
代表取締役CEO
荒木 啓充 氏
在来寄生蜂によるサシバエの生物的防除
〜 牛・人・環境にやさしい、持続可能な新たな畜産害虫管理 〜
◆キーワード
畜産害虫サシバエ、在来寄生蜂、生物的防除、アニマルウェルフェア、牛伝染病抑制
◆プロフィール
製薬企業、国内外のバイオベンチャー・大学にてゲノム解析を中心とした研究開発および事業開発に従事。
国内バイオベンチャーでは主任研究員としてIPOに貢献。九州大学ビジネススクール在籍時には、大学発技術の事業化支援や産学官連携の推進を担当。2025年に株式会社Arthronを創業。博士(システム生命科学)。
◆会社紹介/技術説明
Arthronは、九州大学・松尾研究室の研究成果を基に設立された昆虫系スタートアップです。畜産害虫サシバエに対し高い寄生能力をもつ在来寄生蜂・キャメロンコガネコバチ(通称キャメロン)を活用した、生物的防除ソリューションを展開しています。
サシバエは哺乳類の血液を主な栄養源とする吸血性の昆虫で、鋭い口器で家畜に痛みとストレスを与えて生産性を低下させるうえ、牛伝染性リンパ腫やランピースキン病などの感染症も媒介します。既存の防除手段は効果が限定的で、現場負担も大きいのが課題となっています。
キャメロンによる防除は、薬剤耐性の懸念がなく、キャメロンが自律的にサシバエを探索・制御するため大幅な省力化と、環境負荷も低いのが特長です。脱炭素・サステナブルな畜産が求められる中で、Arthronは、「牛にも、人にも、地球にもやさしい」持続可能な畜産の実現を目指し、国内外での展開を加速していきます。

EUVフォトン株式会社
代表取締役
浅野 種正 氏
極端紫外光(EUV)の照射・解析で半導体用材料開発を短TAT化
◆キーワード
EUV、半導体、リソグラフィー、レジスト、ペリクル、フォトマスク
◆プロフィール
東京工業大学大学院修了。工学博士(1985)。同大学、九州工業大学、九州大学にて半導体デバイス・プロセス技術の研究に従事。国内・国際学会の企画運営を多数担うととともに、国の産業クラスター政策の実行組織、ピュリフィケーション研究会などの民間組織の設立運営などを通して半導体学術・産業界に幅広いネットワークをもつ。
◆会社紹介/技術説明
EUVを使った半導体リソグラフィーは2018年に生産利用が開始されて以後、先端半導体の製造に不可欠な技術としていっそうの高度化開発が進められています。
弊社は、材料開発向け機能をもたせたEUV照射装置と材料分析装置群を自社設備として保有し、フォトレジスト等の半導体製造用材料へのEUV照射~分析・解析~コンサルティングまでを一貫して提供する国内唯一の民間企業です。分析・解析・コンサルティングには九州大学がもつ豊富な分析機器群、高度な解析知見も活用します。発明から実用化までの開発が短期間で繰り返される半導体産業において、従来は海外に依存してきた材料開発向けEUV照射を国内でできるようにし、アクセシビリティと短TATを特長に素部材メーカーのQCD向上に貢献します。

株式会社JCCL
代表取締役
梅原 俊志 氏
九州大学発の低コストかつ高効率なCO₂回収技術で世界のカーボンニュートラル実現を目指して
◆キーワード
脱炭素、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、CCUS、CO₂回収、アミン含有ゲル
◆プロフィール
慶応義塾大学院修了後、1984年日東電工株式会社入社。機械エンジニアとしてプロセス開発業務に従事、2010年にオプティカル事業部門長に就任し、スマートフォン市場の拡大に貢献。2019年には代表取締役専務執行役員CTOに就任。2020年退任後、上場企業の社外取締役、北海道大学理事などの役職を務めながら、2023年4月に株式会社JCCLの代表取締役に就任。幾多のキャリアで蓄積した経営力、知財戦略、人脈等をJCCLに注いでいる。
◆会社紹介/技術説明
JCCLは、世界のカーボンニュートラル達成に貢献すべく2020年に設立された九州大学発スタートアップで、独自のCO₂回収技術のグローバルスタンダード化に向け、技術開発及び事業開発を進めています。
当社では「アミン含有ゲル」という特許材料をコア技術として、低コストかつ高性能なCO₂回収プロセスを実現し、回収装置の上市まで達成しております。
当社の回収プロセスは、50℃程度の低圧蒸気を流すだけでCO₂の回収が可能なため、アミン吸収液を使った手法と比べ、最大4分の1までエネルギーコストを低減できます。また、水分に強いという特長を生かし、吸収材の乾燥工程も不要です。
今後、JCCLの技術の社会実装をさらに加速させるため、パートナー企業とともに地球規模のCO₂回収・利活用に向けた課題解決に貢献してまいります。

九州大学大学院
システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門
准教授
奥村 賢直 氏
農業×プラズマ:種子と堆肥を活かす次世代アグリテックの挑戦
◆キーワード
プラズマ農業、堆肥活性化、種子処理、環境調和、単収向上
◆プロフィール
九州大学准教授。非熱プラズマを活用した農業技術に関する研究と社会実装を推進中。特に、堆肥や種子に短時間照射することで環境適応性や収量向上をもたらす技術の実証を進めている。PARKS等の事業化支援にも採択され、スタートアップ創出を目指す。
◆会社紹介/技術説明
当研究室では、空気プラズマを用いた堆肥・種子処理技術を開発し、環境負荷を抑えながら作物の生産性を向上させる循環型農業を提案しています。プラズマ照射堆肥により、従来より少ない施用量で安定した収量を実現するとともに、サトウキビなどで再現性のある効果を得ています。また、種子照射技術では、発芽促進や収量・耐性向上に寄与する可能性を見出しており、地域の資源循環や持続的農業モデルへの応用を進めています。現在、実証と事業化を加速中です。

九州大学大学院
理学研究院 化学部門
教授
徳永 信 氏
担持金ナノ粒子を用いる脱硫技術による酒類の品質保持と改良
◆キーワード
担持金ナノ粒子、日本酒、焼酎、硫黄化合物、吸着脱硫
◆プロフィール
1995年名古屋大学大学院理学研究科修了、ハーバード大、理研、北大を経て2006年より現職、専門は有機化学、触媒化学。九大着任後、固体触媒(金ナノ粒子などの担持貴金属触媒)の分野も手掛け、有機化学+固体触媒+他分野を融合した研究を展開。そのひとつとして、酒類などの飲料からの吸着脱硫も行っています。
◆会社紹介/技術説明
日本酒はやや高い温度で保存すると老香(ひねか)と呼ばれる硫黄臭が発生します。また、焼酎や泡盛では蒸留の際に硫化水素を始めとした様々な硫黄化合物が発生し、これを蒸発させるため出荷までに3か月から1年の期間を要します。我々はこれら悪臭の原因となる硫黄化合物を担持金ナノ粒子で吸着除去することに成功しました。老香を除去したり、蒸留酒の出荷までの期間を短縮できたりするほか、老香がなく熟成香のみの熟成酒(日本酒)というこれまで存在しなかったお酒も創り出すことができます。
また、最近数年で、有機化学や錯体化学と融合した手法で担持金ナノ粒子を安価に大量に生産する技術も確立しました。具体的な製品化などについても紹介したいと思います。

九州大学大学院
システム情報科学研究院 情報知能工学部門
准教授
福嶋 政期 氏
非接触型VRゴーグルの社会実装に向けて
◆キーワード
VRゴーグル、HMD、空中像、非装着型、テーマパーク、B2B向けVR
◆プロフィール
2013年、電気通信大学大学院情報理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。科学技術振興機構さきがけ専任研究員、東京大学大学院情報理工学系研究科助教を経て、2022年より九州大学大学院システム情報科学研究院准教授に着任。在学中に米国MIT MediaLab Camera Culture Groupへ留学。VRの研究に従事。
◆会社紹介/技術説明
我々は現在、装着を伴わずにVR映像を体験可能とする「非接触型VRゴーグル」の実用化に取り組んでいます。従来のVRゴーグルは、高い没入感を提供する一方で、装着負荷や身体的疲労、衛生管理の課題から長時間の使用に制限があるのが現状です。本プロジェクトでは、両眼映像を空中に立体的に結像させる光学技術を開発し、椅子に座るだけでかぶらずにVR体験を可能とする新しい提示システムを実現しました。
まずは、機材管理や人件費面で運用負荷の大きいテーマパーク等の事業者を導入先とし、将来的には教育、医療、観光、文化施設等への展開を通じて、より快適なVR体験の社会実装を目指します。